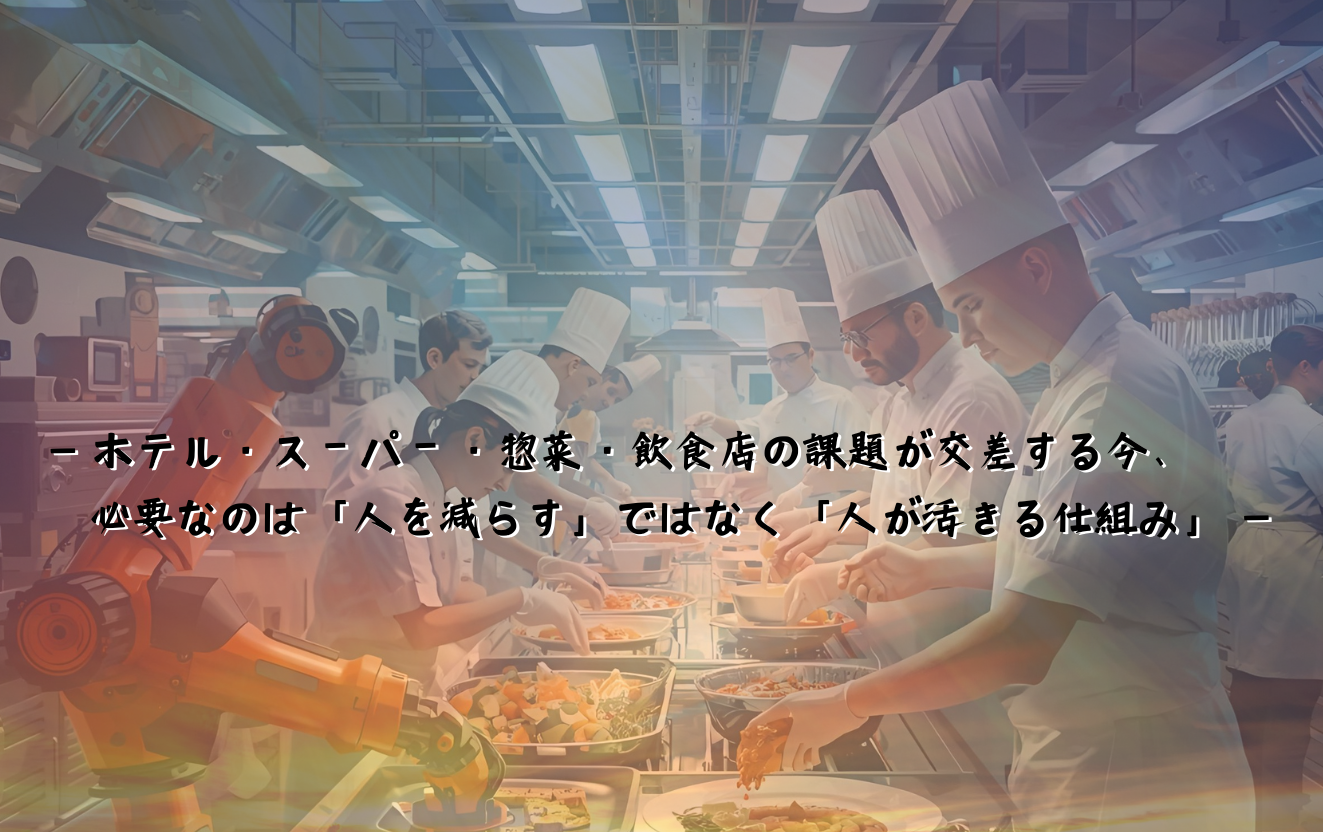
“人手不足倒産”は長年の課題でしたが、2025年に入り、状況はいっそう深刻さを増しています。
帝国データバンクによると、2025年上半期の人手不足倒産は202件と初の200件超え。飲食店倒産も458件と、上半期として過去最多を更新しました。※
一方で、女性・高齢者・外国人の労働参加は数字の上では伸びています。
それにもかかわらず、ホテル・スーパーの惣菜部門・飲食店などの現場では、
・採用できない
・入っても続かない
・育っても定着しない
といった声が後を絶ちません。
つまり本質は、“人がいない”のではなく、“人を活かしきれる仕組みが整っていない”ことにあります。
ここでは、厨房の現場に共通する課題を5つの視点から整理し、“人が活きる厨房づくり”へのヒントを探っていきます。
※出典:帝国データバンク「全国企業倒産集計2025年上半期報」
目次
- 1.採用できても「戦力化できない」現場の現実
- 2.「人が集まらない」厨房の構造的な課題
- 3.“人が活きる厨房”に必要なのは、現場の再設計
- 4.「人手不足倒産」を防ぐためのアプローチ
- 5.“自動化=省人化”ではない。“人が主役”の自動調理機活用へ
- 6.自動調理機・調理ロボットの 導入メリット5選と成功事例
- 7.服部工業株式会社の業務用調理ロボットOMNI(オムニ)
目次へ戻る
1.採用できても「戦力化できない」現場の現実

アルバイトを採用しても、教育には100〜200時間かかることも珍しくありません。
その期間中に辞めてしまえば、投じた時間も労力も戻ってきません。
さらに調理現場は専門性が高く、「見て覚える」「やって覚える」といった属人的な文化が根強く残っています。
新人がつまずきやすい理由は次のとおりです。
・判断基準が言語化されていない
・経験が必要な工程が多い
・ピーク時に余裕がない
こうした“育成の壁”が、人手不足倒産を生む一因にもなっています。
2.「人が集まらない」厨房の構造的な課題

求人を出しても応募が来ない、来ても続かない。
こうした状況の背景には、厨房特有の負担の大きい労働環境や、人が定着しにくい構造があると言われています。
・高温環境
・長時間労働
・ピーク時の集中
・体力負荷の大きさ
これらは、特に若年層・未経験者にとって参入しにくい要因になっています。
さらに、調理は“長年の経験に裏付けられた繊細な技術”が求められる仕事です。
火加減の見極めや、わずかな温度差・味の変化を判断する力など、すぐに身につけられない専門性も多く、これが新人にとってハードルとなり、結果として定着しにくい要因にもなっています。
こうした状況が重なり、“努力しても人が集まりにくい構造”が厨房に根強く残っているのです。
3.“人が活きる厨房”に必要なのは、現場の再設計

人手不足が続く中で求められているのは、「人を増やす/減らす」といった単純な発想ではありません。
限られた人材が無理なく力を発揮できる“現場の再設計(リデザイン)”が必要です。
厨房の仕事には、
・新メニューを考える発想力
・盛り付けの絶妙な仕上げ
・味の最終判断
・現場全体を見渡す気配り
など、人にしか生み出せない価値が確かに存在します。
一方、経験や勘に左右されやすく属人化しやすい工程も多く、このままでは新人が育ちにくく、ベテランの負担が増え続けてしまいます。
そこで必要なのは、“人が力を発揮すべき領域”と“仕組みで支えるべき領域”の整理。
誰が入っても続けやすい仕組みをつくり、人にしかできない価値に力を注ぐ。
それがこれからの厨房に求められる“再設計”の第一歩です。
4.「人手不足倒産」を防ぐためのアプローチ

近年増えているのは、従業員の退職がきっかけで業務が回らなくなる「従業員退職型」の倒産です。
飲食店で多く見られるほか、ホテル厨房やスーパーの惣菜部門でも同様に“人が抜けた瞬間に現場が回らなくなる”という課題が指摘されています。
背景にあるのは、単なる人員不足ではなく、
・属人化
・過重労働
・教育負担の集中
といった、現場の仕組みそのものの限界です。
まず取り組みたいのは、負担の大きい作業の「見える化」。
・仕込みに過度な時間がかかっていないか
・温度・時間管理など手作業に依存している工程はどこか
・レシピや手順にばらつきはないか
・デジタル化で改善できる点はないか
こうした“日々の小さな改善(スモールDX)”の積み重ねが、辞めにくく続けやすい現場をつくります。
そして大切なのは、省人化そのものを目的にしないこと。
「この職場なら続けられる」と感じられる環境づくりこそ、人手不足倒産を防ぐ最も現実的なアプローチです。
目次へ戻る
5.“自動化=省人化”ではない。“人が主役”の自動調理機活用へ

自動調理機や調理ロボットは「人を減らすための機械」と見られがちですが、今、現場が直面しているのは、“人を減らす”ことではなく、“人が続けられるかどうか”。
採用は難しく、育成も追いつかず、ベテランの負担が増え、新人は定着しにくい。
こうした状況の中で、自動調理機は“現場が止まらないようにするための選択肢”として、いま真剣に向き合うべき段階に来ています。
現場が求めているのは、“人を置き換えること”ではなく、
・品質のばらつきを抑える
・教育負担を軽減する
・重労働・反復作業の負荷を減らす
・少人数でも現場が止まらない仕組みをつくる
といった、“人が働き続けられる厨房を守るための仕組み”です。
自動調理機は万能ではありません。
しかし、採用・育成・定着のいずれかが崩れた瞬間に現場が止まってしまう今、“人が無理なく働き続けられる環境を守るための選択肢”として避けて通れない存在になりつつあります。
人を減らす厨房ではなく、人が活きて働ける厨房をどう守るか。
どの工程を人が担い、どの工程を仕組みで支えるか。
いま冷静に見直す時期に来ていると言えるでしょう。
6.自動調理機・調理ロボットの 導入メリット5選と成功事例
“人が続けられる厨房”を守るために、どの工程を仕組み化すべきか。
その一つの答えが、自動調理機の導入です。
ここでは実際の導入現場で確認されている効果を整理します。
導入メリット5選
- 効率と生産性の向上:調理工程を安定して効率化できる
- 労働力不足の解消:少人数でも運営可能に
- 一貫した品質の保持:誰が操作しても同じ仕上がり
- 安全性の向上:高温・重労働のリスクを軽減
- ランニングコストの削減:人件費などのコストを抑制
成功事例(概要)
実際の導入現場では、調理時間を大幅に短縮しながら、人員やコストの削減にもつながったという結果が報告されています。
ある食品加工の現場では「同じ量を調理する時間を最大で80%以上短縮」する効果も出ています。
より具体的な成果や導入事例をまとめた資料を、下記から入手いただけます。
《自動調理機・調理ロボット導入メリット5選と導入事例》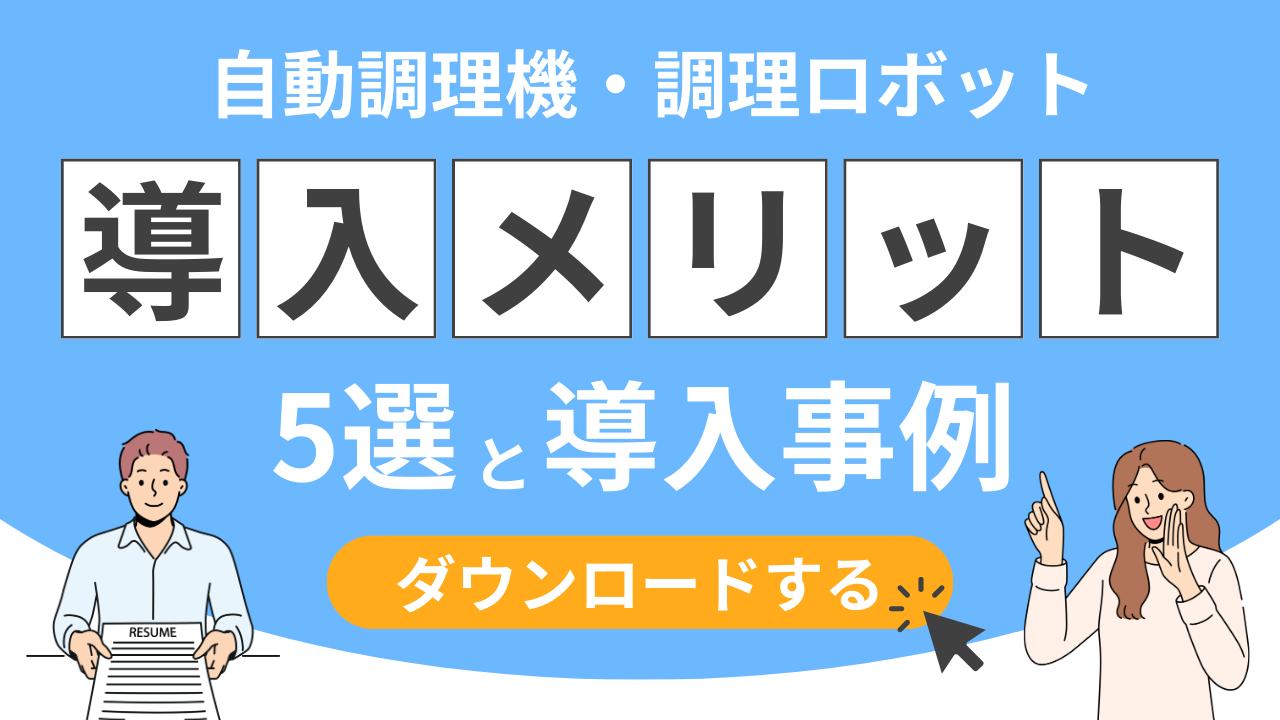
目次へ戻る
7.服部工業株式会社の業務用調理ロボットOMNI(オムニ)
人手不足や属人化が深刻化する中、調理工程の標準化と再現性の確保は、多くの現場で重要なテーマとなっています。
服部工業のロボット回転釜OMNI は、温度管理や攪拌などの工程を自動化し、調理の安定性と作業負担の軽減をサポートします。
導入事例や実際の操作動画も公開しています。詳しくは下記よりご覧ください。
▼“誰でもレシピ通りに”を実現する調理ロボット|OMNIピックアップページ


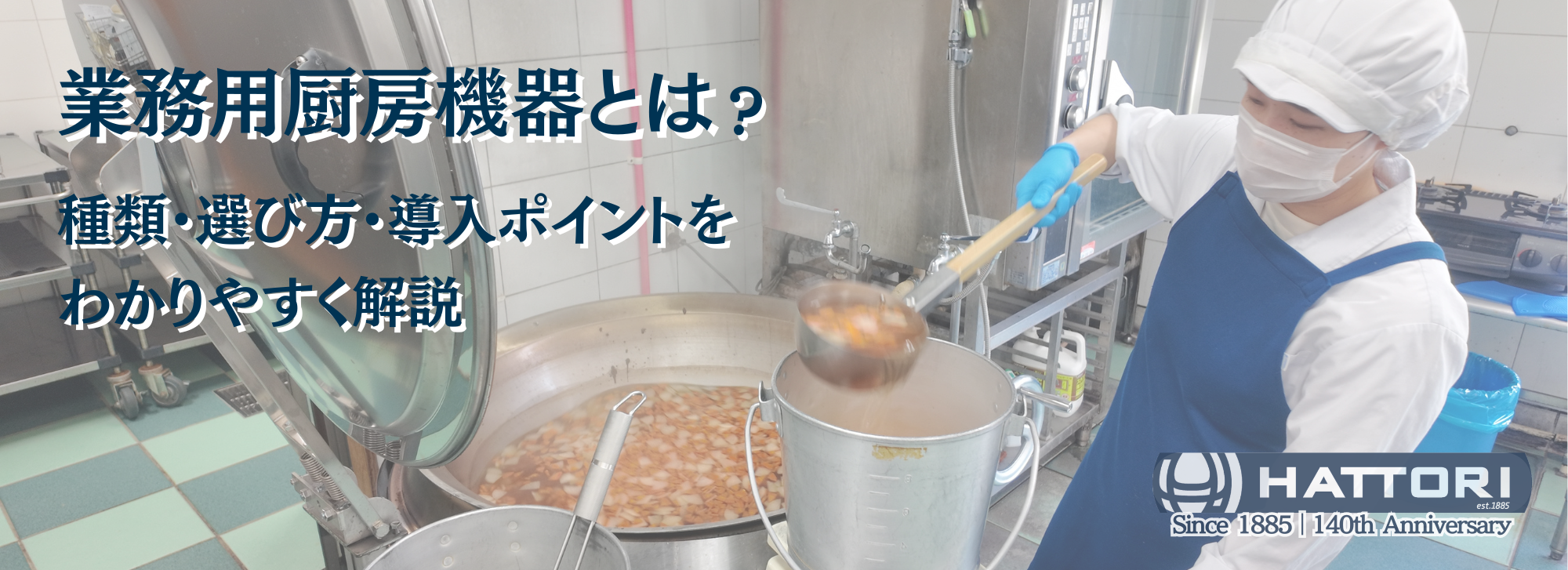

.png)
