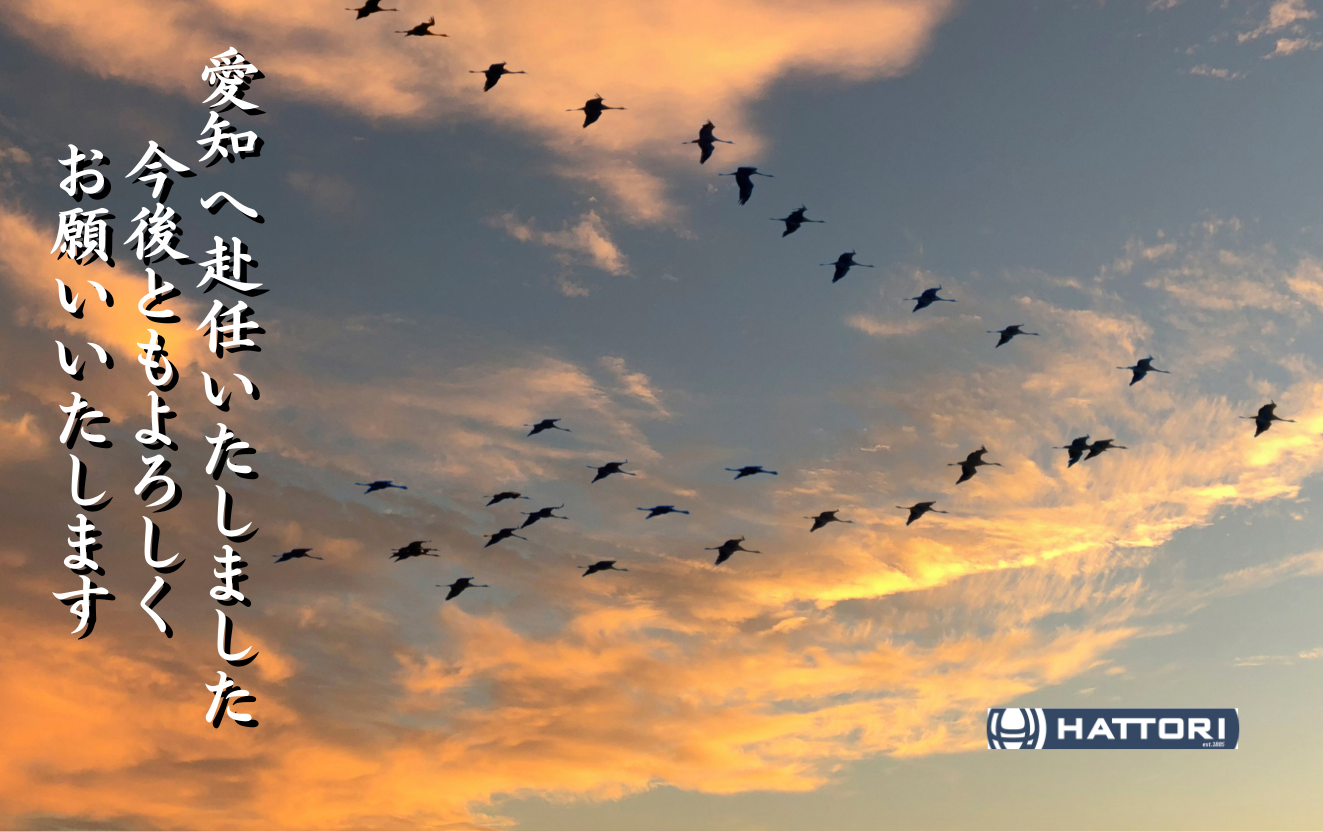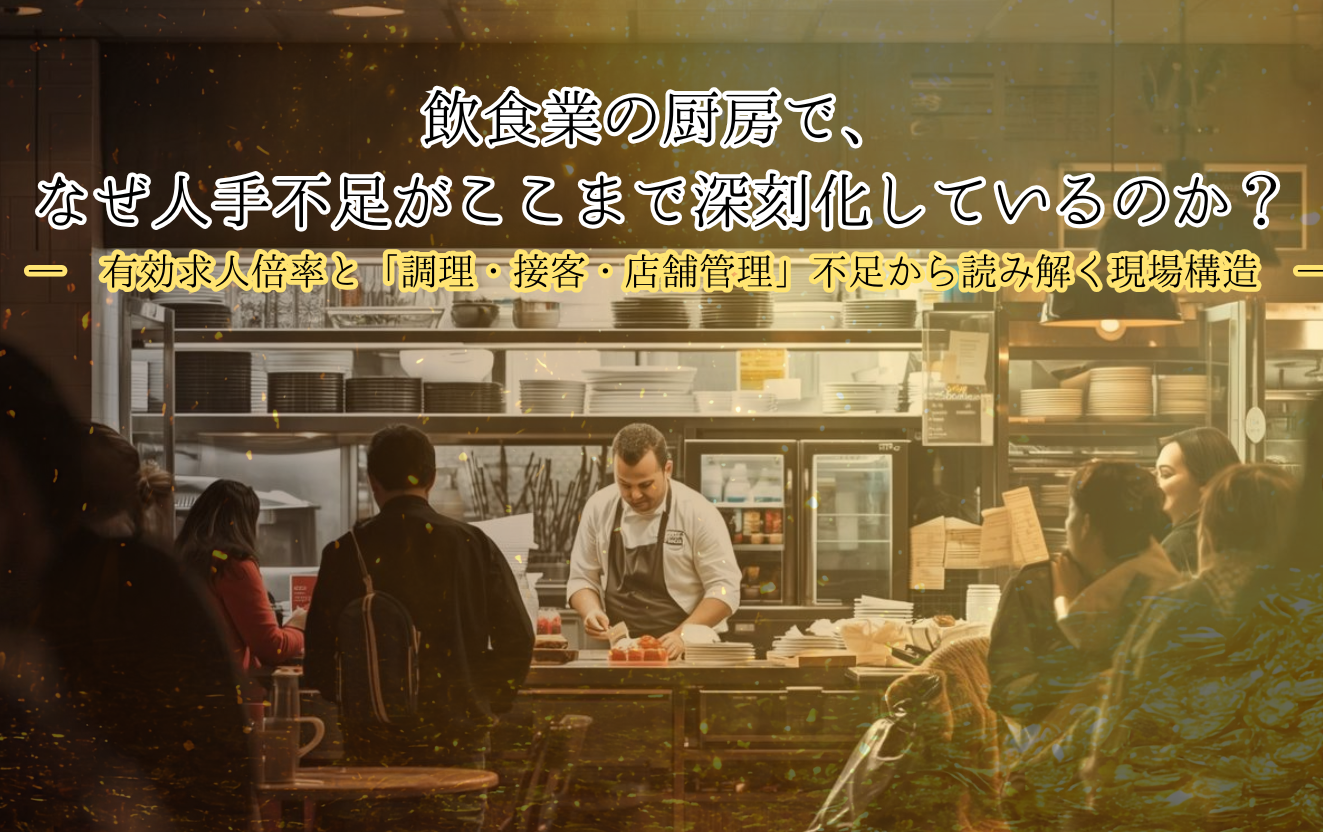.png)
お釜ちゃん俱楽部ニュース428号
「食べるよろこびは、器からはじまる」
過ごしやすい季節となり、秋の味覚が食卓を彩りはじめました。今年はサンマが“当たり年”といわれ、まるまるとした太いサンマが店頭に並ぶ様子が話題になっていました。
そんな旬の料理を、より美味しく、より豊かに見せてくれるのが「料理の衣裳」とも言われる器。なかでも磁器は、料理を引き立てながら、日本の食文化とともに歩んできました。
目次
日本の食器文化と磁器の関係
磁器食器の代名詞ともいえる【有田焼】が誕生したのは、約400年前の江戸初期といわれています。古くから日本料理の世界では「器は料理の衣裳」とされ、料理を引き立てる大切な役割を担ってきました。
磁器には、
・白さと滑らかな風合いで、料理の色や質感を引き立てる
・吸水性がほとんどなく水や汚れが染み込みにくいため、清潔さを保ちやすい
・強度が高く、日常使いにも適している
といった特長があります。
江戸時代以降、磁器の和皿には草花や動物など自然のモチーフが描かれ、季節感やおもてなしの心が表現されてきました。これらの器は、客人をもてなすうえで欠かせない重要な要素となりました。
やがて磁器は生活に根づき、料理とともに発展を遂げてきました。現代の食卓では和食だけでなく、カレーやラーメン、ハンバーグといった多彩な料理を引き立てています。
多様性を受け入れながら調和を大切にする。そんな日本独自の食器文化が育まれてきたのです。磁器は、その歩みを支える存在といえるでしょう。
器が変える、食事の時間
そして、食器は料理をおいしく見せ、食欲や満足感にも影響を与えます。日常の食卓だけでなく、給食や介護など大人数に向けた現場でも、その役割は変わりません。
一方で、高齢者施設や介護施設では、見た目よりも安全性や軽さを重視した食器が多く使われています。それはもちろん大切なことですが、「味気ない」と感じられることもあるのではないでしょうか。
食事は単に栄養を摂るだけではなく、暮らしの尊厳や毎日の楽しみを支える大切な時間です。見た目に彩りがあり、手に取ったときにぬくもりを感じるかどうかは、入居者の方々の日々の楽しみや食欲にも直結します。
とはいえ、そうした器を選び、管理し続けるのは簡単ではありません。
そこで服部工業のグループ会社アーテックでは、破損や補充の負担を減らし、扱いやすさや衛生面にも配慮した「磁器食器年間レンタルサービス」をご案内しています。
食事が楽しみになるデザインで、入居者の方々には“食べるよろこび”を、スタッフの皆さまには“安心と効率”を。そんな思いから生まれた新しい取り組みです。
「磁器食器年間レンタルサービス」の詳細はこちらから
※グループ会社アーテックのホームページへ飛びます。