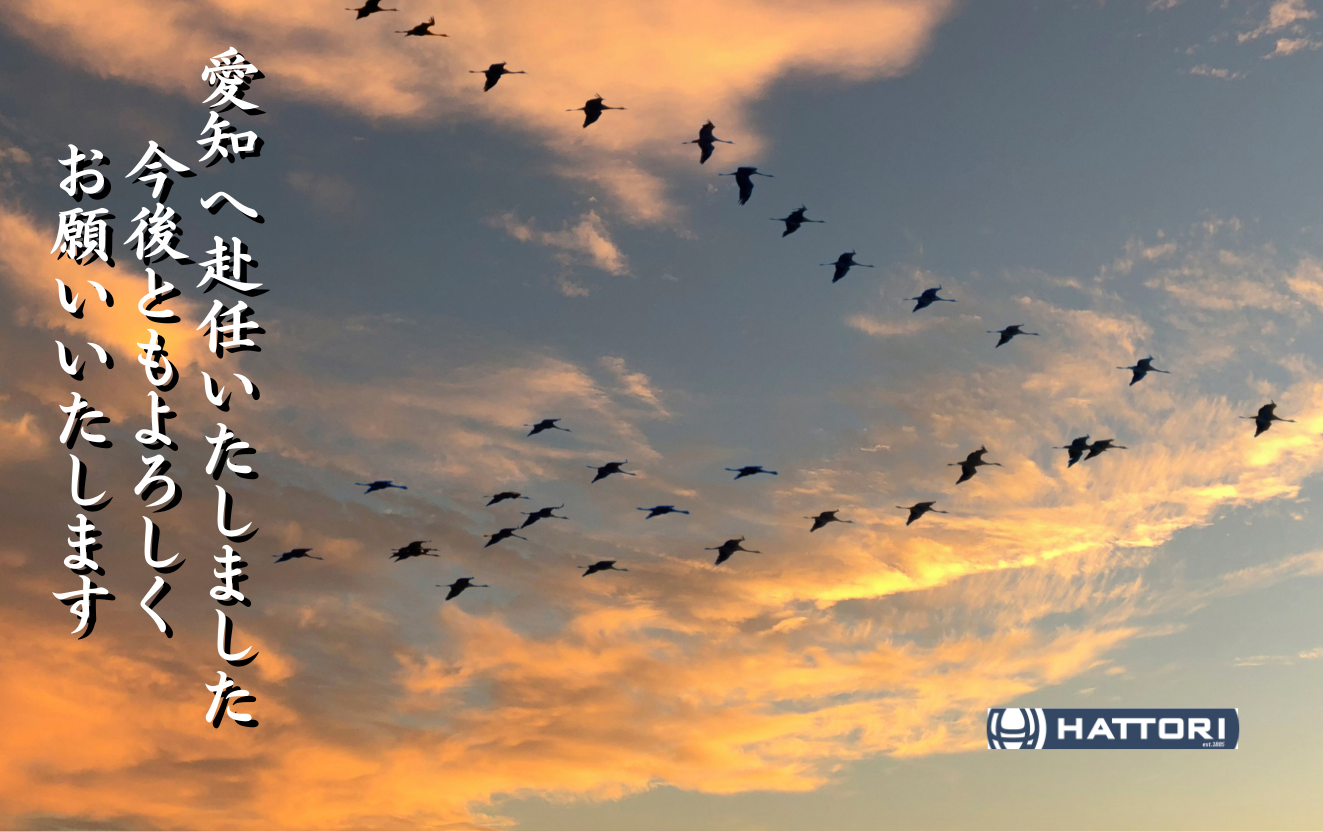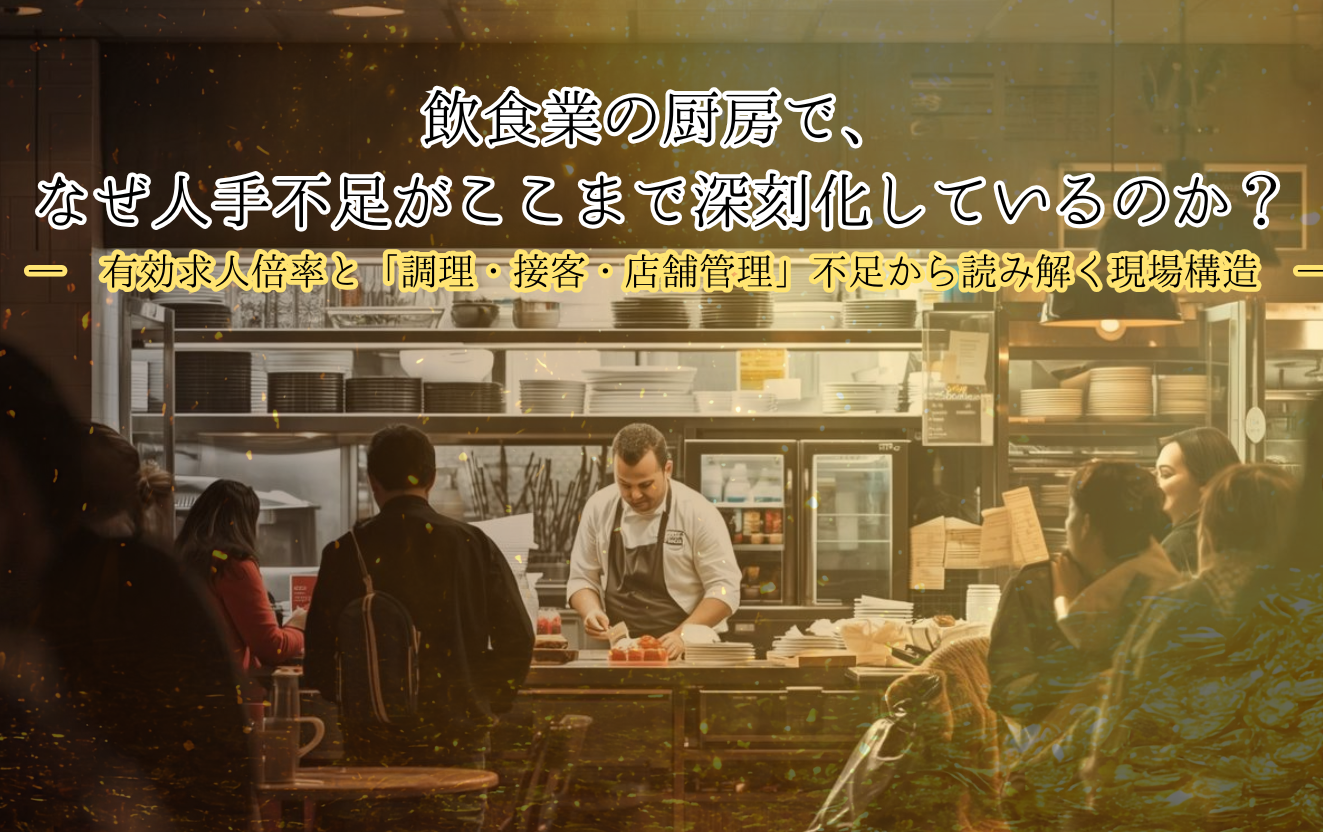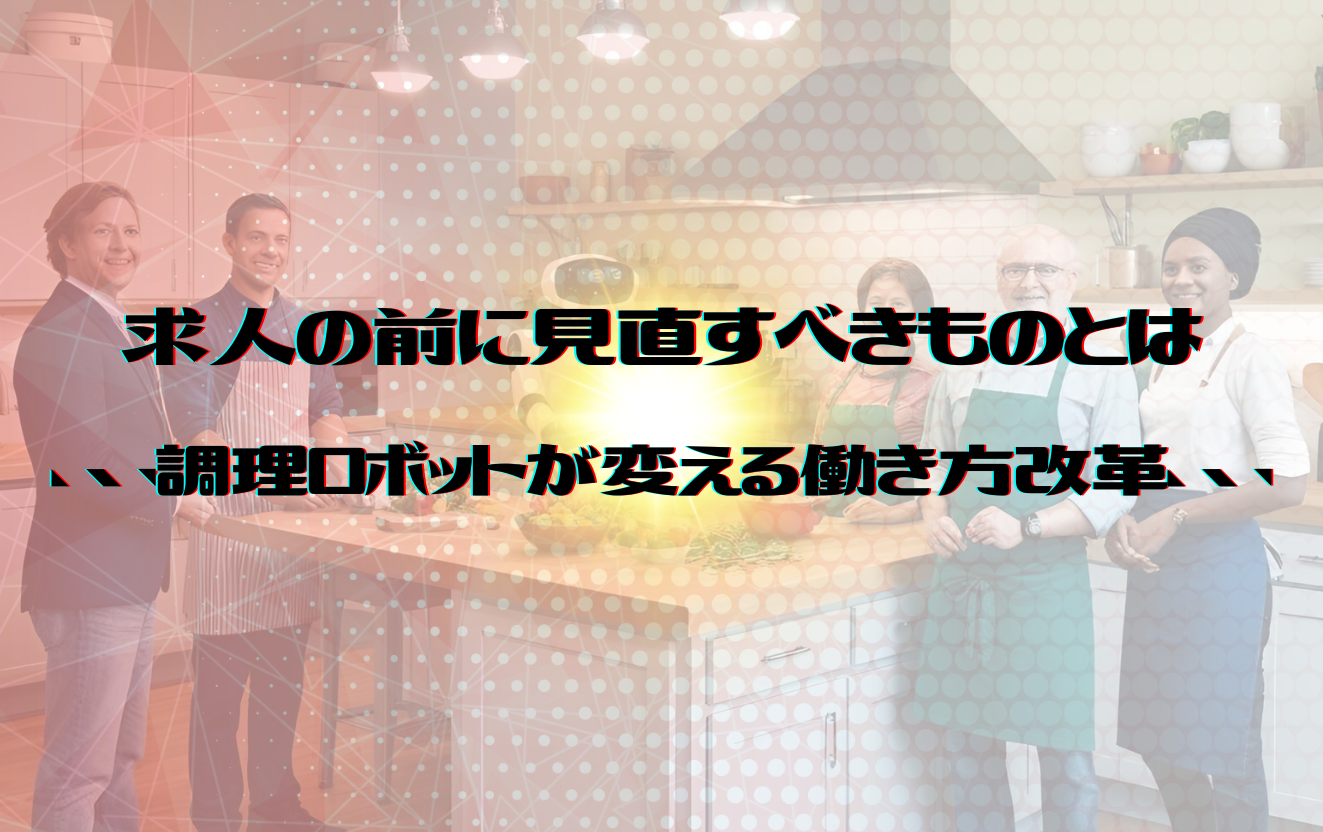
飲食業界の人手不足は、もはや一時的な課題ではありません。
それでも、求人を出せば「人」は集まります。
けれども集まる人と、現場が求めている人が一致しない─そんなすれ違いが、今の厨房の悩みの本質かもしれません。
高温・重労働・属人性─従来の「人に合わせてもらう」厨房の在り方は、いま確実に変化の必要に迫られています。
このコラムでは、「人手不足」そのものではなく、「人手不足が問題になる厨房構造」こそ本当の課題であることを、多角的に掘り下げていきます。
そしてその先に見えてくるのが、「人に頼らず、人を活かす厨房」へのシフト。
調理ロボットや自動化の導入が、厨房にどのような可能性をもたらすのか─そんな未来を、一緒に考えてみませんか?
目次
- 1.その求人票に、いつまで希望を託しますか?
- 2.必要な人材がいなくても現場は回る─の逆説
- 3.「ベテランが辞めたら終わり」な厨房からの脱却
- 4.「うちはまだ手作りにこだわっている」─という呪縛
- 5.「自動調理機=高コスト」という誤解
- 6.厨房改革は「未来の話」ではなく、「いま選べる現実」
- 7.自動調理機・調理ロボット 導入メリット5選と成功事例
- 8.服部工業の業務用調理ロボットOMNI(オムニ)
目次へ戻る
1.その求人票に、いつまで希望を託しますか?

「やる気のある人材、急募!」
かつてはこの一言だけで、何通もの応募が舞い込んだ時代がありました。
現在も、求人を出せば“人”は集まります。実際、厚生労働省の統計によれば、総就業者数は2025年現在、過去最高水準を記録しています。※
しかし、その中身を見てみると─増えているのは、シニア層・女性・外国人労働者といった、これまで厨房現場では“戦力”として想定されてこなかった人々。
飲食業界でも採用の裾野が広がっていることは確かですが、「来てほしい人材」と「実際に来てくれる人材」の間に、見えないギャップが生まれているのです。
問題は、「人が来ない」ことではなく、「その人たちでどう回すか」を考えられていないこと。
─たとえば、重たい鍋を煽る、高温の釜に張りつく、数年かけて味を覚える…
そんな“昔ながらの厨房”では、せっかくの新しい力も活かしきれません。
※出典:総務省統計局「労働力調査 (基本集計)」
2.必要な人材がいなくても現場は回る─の逆説

「必要な人材がいない? なら、“必要じゃない厨房”にすればいい」
一見、暴論のように聞こえるかもしれません。しかし、その裏には厨房の在り方そのものを見直すヒントが潜んでいます。
実際、多くのホテル、飲食店、スーパーの総菜部では、求人を出せば一定数の応募があります。
つまり、“人がいない”のではありません。
今、現場に集まっているのは、シニア層や女性、外国人など、多様なバックグラウンドを持つ人たちです。
けれど、「求めていた理想の人材像とは違う」と感じる現場も少なくないでしょう。
体力勝負の調理、高温の厨房、自分の勘で味を決めるベテランの技─
これまでの厨房は、“選ばれた一部の人だけが戦力になれる”構造でした。
しかし、こうした「属人性の高い作業」が前提となっている限り、せっかく来てくれた人たちも力を発揮できません。
必要なのは、“一部の人しか扱えない厨房”を、“誰でも使える環境”へと変えていくことです。
そして今いる人で現場を動かすには、「効率化・自動化・省力化」が欠かせません。
「理想の人材を待つ」のではなく、「今いる人で、現場を動かす」。
そのために必要なのは、“人が厨房に合わせる”のではなく、“誰にでも合う厨房をつくる”という、発想の転換なのです。
3.「ベテランが辞めたら終わり」な厨房からの脱却

「あの人が急に休んだら、このメニューは無理」─そんな属人化した厨房、まだ残っていませんか?
料理人の勘や技術に依存しすぎる体制は、裏を返せば“リスクの塊”です。
スタッフの異動や退職が、味のブレや品質低下を引き起こす。そのたびにクレーム対応や教育コストが膨らむ。
属人化のリスクを減らすには、「誰がやっても同じ味」を実現できるプロセス設計が必要です。それには、調理の標準化・自動化という視点が欠かせません。
人が変わっても味は変わらない─そんな厨房を目指す時が来ています。
4.「うちはまだ手作りにこだわっている」─という呪縛

「うちは手作りの温もりが売りだから」─そう語る店主や料理長の気持ちは、よくわかります。
ただ、その“こだわり”が、今の厨房にとって足かせや非効率の温存になっていないか、立ち止まって考えてみる価値はあります。
たとえば、「誰が作っても同じ味に仕上げるために」と、手順が細かくマニュアル化され、かえってオペレーションが複雑になっている現場。
または、「誰でも作れるように」とレシピ自体が単純化されてしまい、メニューの幅が狭くなっている現場。
それでも「手作り感を守っている」と言えるでしょうか?
本来、“こだわり”とは品質や多様性を支えるためのものであって、スタッフの負担や表現力の制限になるものではないはずです。
一方、いまある自動調理機や調理ロボットは、かつて思い描かれたような“人の代わりに作る機械”ではありません。
人の味を、技術で補完し、安定させ、再現する─まさに厨房の「相棒」として進化している存在です。
高精度な温度制御、自動調味、タイミング管理など、料理人が「美味しさ」に集中できる環境を支えながら、現場の負担も軽減してくれる。
“誰が作っても同じ味”を、人とロボットのチームワークで実現する時代が、すでに始まっています。
「手作り」にこだわるなら、むしろその価値を守るために、“どう作るか”に固執せず、“何を提供できるか”に目を向ける。
厨房の進化は、“人の代替”ではなく、“人の可能性を広げる”ためにあるのです。
目次へ戻る
5.「自動調理機=高コスト」という誤解
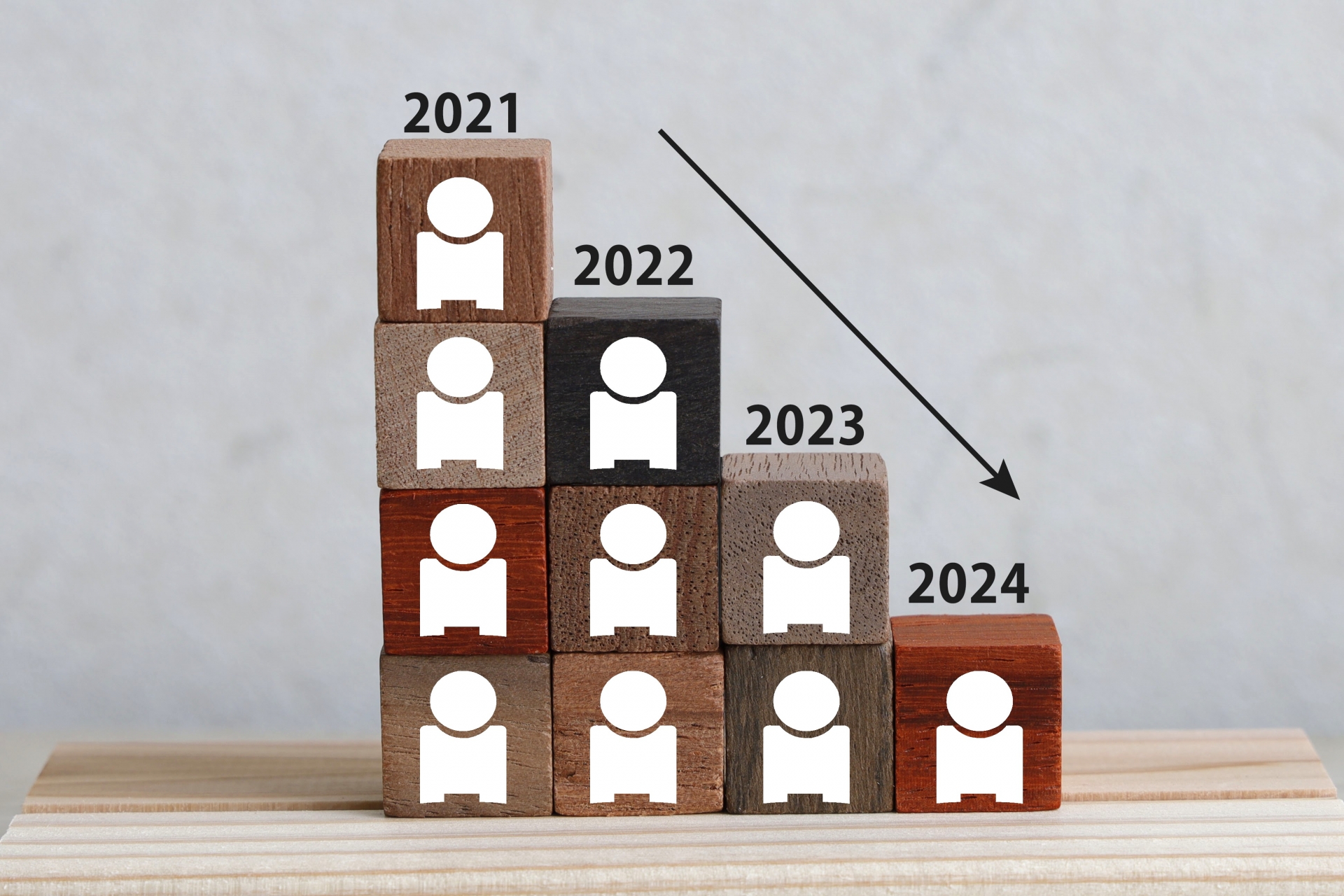
「うちにはそんな高価な機械を入れる余裕なんてないよ」
そう考えて、今もすべての作業を手作業で回しているお店は少なくありません。
でもその“高い”というイメージ、本当に正しいでしょうか?
たとえば、時給1,200円のパートスタッフを1人雇用した場合、月20万円近い人件費がかかります。
もし3人採用して、数ヶ月ごとに入れ替わるような状況なら─その都度、採用・教育・引き継ぎ・管理のコストが積み重なり、1年で数百万円単位の支出になることも珍しくありません。
しかも、最低賃金はこの10年で約35%上昇しています。※
人手不足や物価上昇の影響で、今後も人件費が下がる見通しはほぼゼロ。
つまり「毎月の支出」は今後もじわじわと増えていくのです。
一方で、自動調理機のような厨房設備は、初期費用こそあるものの、導入後のランニングコストは予測しやすく、変動も少ない。
機械は突然辞めたり、調子が悪くなったりしません。定期的なメンテナンスさえしていれば、黙々と、安定して働き続けます。
「高くて導入できない」のではなく、
実は最もコストがかかり続けているのは、“人を前提にした厨房”そのものかもしれません──
そう考えてみると、これまでの“常識”が、少し違って見えてきませんか?
※出典:厚生労働省「地域別最低賃金改定状況」
6.厨房改革は「未来の話」ではなく、「いま選べる現実」

「自動化」と聞くと、最先端の大企業や大規模チェーンの話に思えるかもしれません。
しかし、実際には、中小規模の飲食店やスーパーの総菜部でも導入が進んでいるのが現状です。
これまで人手に頼っていた工程が少しずつ置き換わり、厨房は“特定の人だけが扱える場所”から、“誰でも扱える場所”へと進化しつつあります。
調理ロボットや自動調理機は、もはや特殊なオプションではなく、厨房の標準装備のひとつになり始めているのです。
しかもこれは、「いつか必要になる」ではなく、「今から選べる選択肢」。
早く取り入れた現場から順に、人手不足のストレスから解放され、味も、作業も、働き方も安定しているのが現実です。
厨房の働き方改革は、“未来の構想”ではありません。
あなたの厨房で、今この瞬間から始められる「現実的なアップデート」なのです。
7.自動調理機・調理ロボット 導入メリット5選と成功事例
今から自動化を進めたいと思った時、最初に見ていただきたい内容を資料にまとめています。
機器の選び方や導入事例も記載しておりますので、是非ご覧ください。
- 飲食業界の人手不足と自動化の波
- メリット5選
- 成功事例4社
- お客様にあった機器を選定するために
- 服部工業の自動調理機器一例
- 同じ量の製造作業時間を80%以上短縮
- 同じ量を製造する人員を 50%削減=人件費が半減
- 同じ量の製造でも作業時間を80%以上の短縮
- 調理できる量が格段に増えた
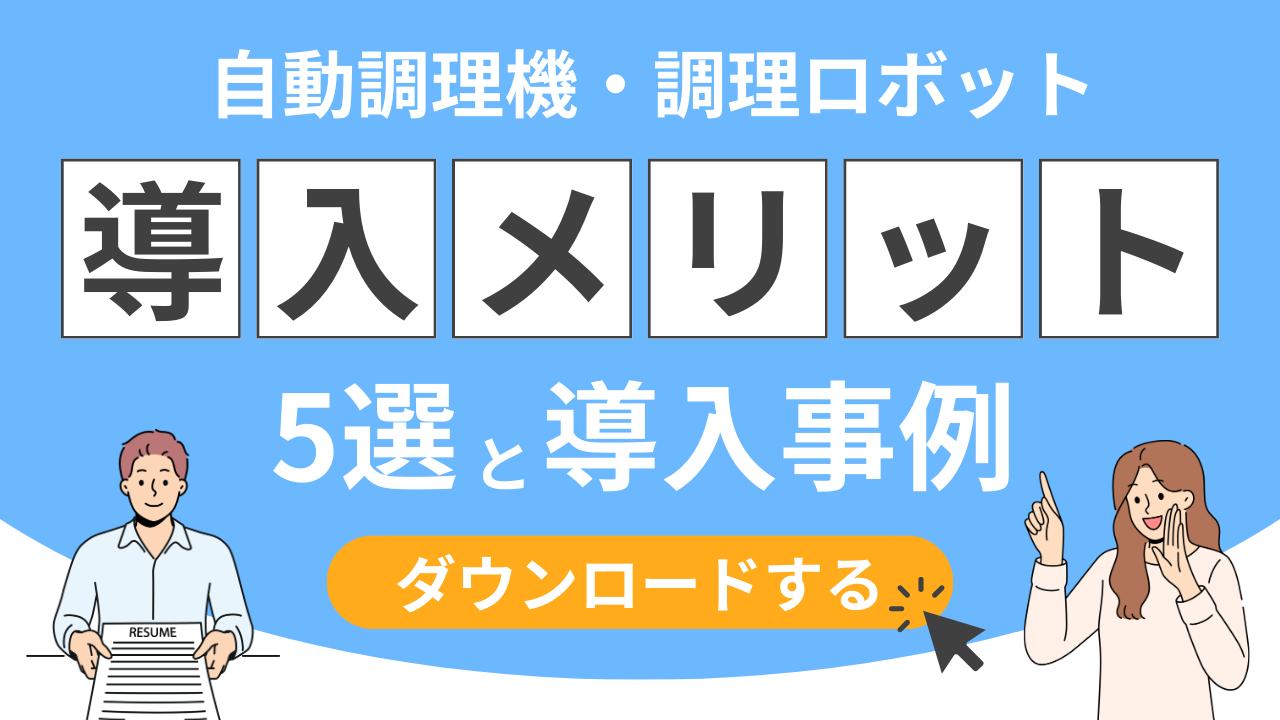
目次へ戻る
8.服部工業の業務用調理ロボットOMNI(オムニ)
経験に左右されない、誰でも“おいしい”がつくれる厨房へ。
服部工業のロボット回転釜OMNIは、温度管理・調味料投入・攪拌まで自動で制御し、誰が使っても安定した味を再現。
多様なスタッフが安心して調理に関われる、新しい厨房環境づくりをサポートします。